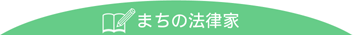 |
|
|

|
相続、遺言、成年後見、消防計画、防災計画、防火対象物定期点検報告制度
自衛消防隊訓練、防災教育、共同防火管理、会社設立、相続 等 おまかせください
|
TEL : (03) 3698-3914
FAX : (03) 3698-7539
東京都江戸川区瑞江1丁目19番11号
| |
|
|  |
|
|
 |
|
 地区防災計画を考える
地区防災計画を考える
26年4月から地区防災計画がスタートしました。
内閣府の資料によれば、地域防災計画書は23区の場合、区が作成しますが、町会や自治会、コミニティなどは地区の特徴を反映して地区防災計画書を作成し、地域防災計画書へ要望できるとのことです。
勝手な要望は論外ですが、地区の方々が自分の事として考え、さらに行政へ提案できる仕組みとなります。
専門家のアドバイスは必要と思いますが、それにもまして町会等の役員の方々の知識と意識が大事です。
自分の事ととらえ、イメージすれば、何が起こって、何に困って、どうすればいいか、どうしておけばいいかが分かります。
後は行動あるのみです。
分かれ目は行動するかしないかの1歩・半歩の違いです。
これは皆さんへお伝えしていることに加え、私自身への声援でもあります。
ファイト!
 相続・遺言を考える
相続・遺言を考える
世の中には危機管理といわれてるものがたくさんあります。
人命に関すること、環境に関すること、教育に関すること、国防に関すること、災害に関すること、健康に関すること、経済に関すること、等々書き出せばきりがありません。
項目別に分けると縦割りの関係になりますが、項目別の中で私たちは生活しているわけではありません。
この社会で今生活しています。
この、今生活しているという「横ぐし」を通して時間軸で考えると、「思いを伝えること」、「財産を引き継ぐこと」を戦略的に行うことの重要性が見えてきます。
時間の経過により、人は必ず死に至ります。縁起のいい悪いという話ではありません。
現実に対策を講じておくべき大きな課題です。
準備次第で結果は大きく異なります。
相続は死後の手続き、遺言は死への準備と思われてる人も沢山いるようです。
遺言は思いを伝え、その思いを具現化するのが相続手続きと考えてみてください。
そんな大事なことを人任せにできますか?
「後はみんなで仲良くしてね」と言われてもその処理は大変です。
思いは必ず実現します。
みんなが幸せになり、ありがとうと感謝する台本を描いてみませんか?それが遺言の一つの形だと思います。
知識と意識が大事です。
 災害時協定について思うこと
災害時協定について思うこと
「●●と△△は災害時応援協定を結びました。」という記事が掲載されるを見ることが多くなりました。
意識の高まりを感じる反面、本当にできるの?と考えさせられるものもあります。
災害時の協力協定を結ぶことを否定するものではません。
どちらかといえば、歓迎する立場です。
ポイントは二つ。
一つは災害時の協定内容の具体性、実効性です。
もう一つは、その裏付けとなる平(日常)時のお互いの活用です。
平時と災害時は時間的に連続しています。
日常の活動の延長線上に災害時の協定が成り立っています。
時間とともに状況は変化します。その変化に対応するのが対策であり、具体的活動です。
そのためにも、時間を意識したイメージで描くことは重要です。
私たちは知識については十分あります。現代ほど災害に対して情報発信されている時代はありません。では、意識はどうでしょうか?知識があっても意識がないと何もしないで終わります。時間に余裕があるとき(災害が発生していない今)が一番準備に適した時です。災害協定を見直すのはいつですか?・・・今でしょう!
今やらないと、明日もやれません。
そうこうしているうちにその時が発生し、準備不足が露呈します。
協定の見直しは、やっぱ、いまでしょう! そう思いませんか?
 2011年12月31日に思うこと
2011年12月31日に思うこと
東日本大震災の影響もあり、危機管理のお問い合わせが多くなりました。講演もあちこちらで行っています。でもね、ヒントはお話できてもそれを聞いてやるかやらないかが結果のすべてです。
BCPも作ったけど役にたたなかったとよく聞きます。役に立たなかったのではなく役になてられなかったのではと思います。作ったら造りっぱなし、検証も訓練もしていなければ役に立ちようがありません。
BCPという表現を使わなくても、あたりまえのことを準備して、ちゃんとできましたというところも少なくありません。
言葉に惑わされないで、やるべきことをやっていく。危機管理はイメージ力です。リアルにイメージして対処を考えれば、おのずと答えは見えてきます。
今年はあらゆるものが試された一年だったと思います。
政治、経済、環境、安全、防衛、そのほか沢山の事象が思い浮かびます。
これからは漠然とではなく、ポイントを定めて狙い撃ちするぐらいの眼力が必要だと思います。
できることからやりましょう。そうすれば憂いは少しなくなります。
備えた分だけ憂いなし。新潟の防災士さんがそう語っていたことを思い出します。
何をどう備えるか?イメージしてみてください。2012年につなげるために☆
 テナントの防火管理者の皆さんへ
テナントの防火管理者の皆さんへ
最近、防火管理の実態についての問い合わせが多くなっておりますので、少しご説明します。
防火管理者は防火管理者講習会、効果測定により資格を取得しますが、これで終わりではありあません。正しくはこれからスタートです。社長(権原者:権限の源の意味)の命を受け防火管理の業務を全面的に行なうわけですから、その責任は重いといえます。簡単に資格が取れたのでたいしたことはないと思わないことです。
複合用途ビル(雑居ビルなどで収容人数が30人以上)などでは、不特定多数の人が出入りします。ビル全体として防火管理をみますので、テナントとしては小規模であったとしても、防火管理者を選任する必要がでてきます。消防計画はよく吟味して作成しましょう。雛形どおりの消防計画では、「帯に短し襷に長し」!
自衛消防隊の組織も無理をしないで、優先順位を簡潔にイメージしましょう。特に大事なのは日常の自主点検です。コツコツと日常の習慣付けを行なうのが、ツボ!・・コツです。
<<前のページ
次のページ>>
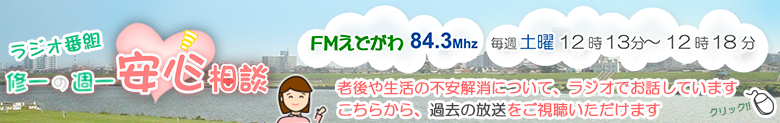
 |
 |
お問い合わせ/ご相談、ご不明な点などございましたら、是非お気軽にお問い合わせ下さいませ。
石井行政書士事務所 http://www.tokyo141.com/
| |
< 石井行政書士事務所トップページ
|
サイトマップ(このホームページの目次) |
|
|