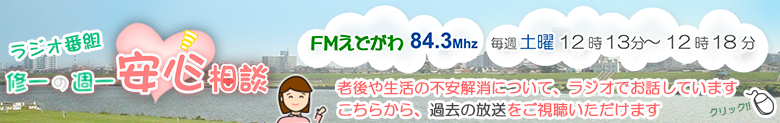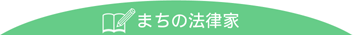 |
|
|

|
相続、遺言、成年後見、消防計画、防災計画、防火対象物定期点検報告制度
自衛消防隊訓練、防災教育、共同防火管理、会社設立、相続 等 おまかせください
|
TEL : (03) 3698-3914
FAX : (03) 3698-7539
東京都江戸川区瑞江1丁目19番11号
| |
|
|  |
|
|
 |
|
 共同防火管理のノウハウ
共同防火管理のノウハウ
共同防火管理とは、読んで字のごとく共同で防火管理をしましょうということです。
誰が?・・雑居ビルを例に取れば、ビルオーナーとテナントの皆さんです。
何で必要なの?・・ビルオーナーといえども、テンナトに貸し出している部分に対して勝手に出入りする事は出来ません。貸している以上、借り手の権利が強いからです。でも、こと防火管理については、テナントの部分に規制や協力を求めることができないと、とても不都合なことになります。店先から通路にはみ出して陳列されていたり、防火シャッターの下に物が置かれていては、避難に支障がでますし、火災の被害を大きくしてしまう結果になります。
雑居ビルに来るお客さんの心・思い・発想をチョット想像してみてください。
1階に喫茶店、2階に診療所、3階に英会話スクールの入っているビルを例にとって説明します。喫茶店にいるお客さんはもしかすると、英会話にきたんだけれど、早いので時間を過ごしているかもしれません。風邪気味なので、診療所に行こうと思った患者さんは、いつも喫茶店に来ている人かもしれません。2階に診療所があったなと知っているから来たんです。子供を英会話スクールに送って、チョットいっぷくという人かもしれません。こんな風に考えると、このビルにいる人は各テナントのお客さんたちです。という発想が必要です。お客さんを「共有している」発想が大事です。
誰も、危険な場所に好き好んで入る人はいません。
テナントの皆さんとオーナーのお互いの協力で安全が維持され守れる仕組みなのです。
これが、共同防火管理の姿勢です。
共同防火管理という用語に惑わされないでください。事業の発展のためには努力が必要です。その一つの形が共同防火管理なのです。
共同防火管理を進める手立てに共同防火管理協議会があります。
(協議会の仕組み・役割は私のホームページにありますので、参考にご覧ください。)
運用のノウハウは当たり前のことを当たり前にすることです。
あるべき姿を実行することが、究極のノウハウです。
ビルの構造・規模・テナントの種類・収容人数など要因によってその姿は異なるでしょうが、本質はビルにあわせた防火管理をすることに他なりません。
でも、なかなか共同防火管理が進まないのも実態です。直接利益にはつながらないと思っている経営者が多いからです。安全はお客さんへのサービスです。お客さんもサービスの悪い店には行きませんよ!努力の成果はこれからはっきりとでてきます。
安全はゲストサービスの基本です。
オーナー、テナントの皆さん、これからが、勝負です。早く気が付いた者の勝ちです!
次回は「誘導灯」についてお話をします。
 番外編「9月1日防災訓練に行ってきました」
番外編「9月1日防災訓練に行ってきました」
番外編
9月1日は防災の日で日本各地で防災訓練が行われました。
夕方のニュースでも多くの訓練が紹介されています。
私は、江戸川消防団に入っていますので、区の行う総合防災訓練にも参加します。また、防災士でもあり、ビルのオーナーからも消防訓練の指導を依頼されます。そして、NPO危機管理対策機構にも会員として大変お世話になっています。このようにいろいろな機会をとらえて訓練に参加し、勉強しています。
9月1日は世田谷区の訓練にいってきました。図上シミュレーションでの訓練が行われました。(訓練内容はホームページでご紹介がなされるかと思いますので省略します。)
訓練は創意と工夫が必要です。同じ事をしていても、災害はすでに想定の範囲を超えています。可能性は少なくても、もし、こうなったらどうしようと・・想定することが必要です。皆さんがいま考えている想定は現実に起こりうるものばかりです。
「無傷で助かるためには・・」と考えるとやれることがありません。「命が助かるためにどうしよう」と考えてください。助けるのは自分の「命」です。究極の選択です。この心構えを忘れないでください。そして助かったら、次に人の命を助けるために、どうしよう・・と行動してください。
こんな感想を持った9月1日でした。
日本テレビのニュースでお天気キャスターの木原さんが防災士のジャンパーを着て、防災をアピールしていました。私も同じ仲間です。皆さんも個人でできることから一緒に始めませんか?
 防火対象物の定期点検報告は誰に任せましょう?
防火対象物の定期点検報告は誰に任せましょう?
防火対象物の定期点検報告制度という言葉は、事業を営んでいる方には耳にたこができるほどよく聞く言葉だと思います。でも、実態がよく分からないという方が多いようです。よく聞いてみると、消防設備の法定点検と混同されているのです。点検の対象が防火対象物(施設全体)に対し消防設備はあくまでも設備の点検です。ざっくり言ってしまえば、建物全体の管理状況を点検するのが防火対象物の定期点検報告制度です。その中には勿論、消防設備の点検結果も反映されています。
(詳しい制度の説明は、消防関係のホームページに解説が載っていますのでご覧ください。)
点検対象施設の管理者は防火対象物点検資格者(業者)の方に点検を発注します。そして点検結果を確認し、報告書に押印し消防署に提出しています。
適切な対応だと思いますが、もう一歩踏み込んで自分の施設を自分で点検し報告することができたらいいのにな~!と思います。
防火管理者の方は一定の経験年数を経た後、防火対象物点検資格者の受講資格を得ることができます。受講しその後の試験に合格すれば、防火対象物点検資格者です。「自分の施設は自分で守る」この基本スタンスがあればチャレンジする価値は充分あると思います。簡単に合格できるものではありませんが、勉強すれば必ず合格できます。資格は取って生かしてはじめて資格です。防火管理は心意気です。安全は認知して行動して初めて手に入れることができるものです。守りの防火管理から、攻めの防火管理にシフトしましょう!社会全体に安全はタダで手に入るものではないと認識されてきています。お金をかけるなら、費用対効果も重要です。差別化する絶好のチャンスです。安全は事業を継続する土台です!
次回は「共同防火管理」についてです。
 防火管理組織と自衛消防隊組織は表裏一体
防火管理組織と自衛消防隊組織は表裏一体
防火管理組織は日常において災害を防止する組織、自衛消防隊組織は災害時に活動する組織と定義されています。
言葉の定義はこれで説明できますが、実際の運用はどうでしょう?
今の時代、日常と非日常(災害時)の線引きがきっちりできるでしょうか?
言葉のあやではなく、実際の問題として考えてみてください。
日常の中にいつ災害が起こるかもしれないという状況をはらんでいるのが今の社会です。消防法において2つの組織を消防計画に盛り込む事が決められていますが、別々の運用をする組織と勘違いしないでください。切り口・見え方の問題で、日常でも非日常でも対応する組織の構成員である個人は同じ人です。一人一人の個人が災害を予防する役割を持ち、また災害発生時には対応しなければならないのです。しかもテンデンバラバラ・好き勝手・思いのままに行動しては結果は見えています。だから組織だって行動しましょうという事になります。それが二つの組織の名称であり、役割となります。ですから、災害時に対応する組織を日常の活動と切り離して考えても意味がないのです。
日常の組織がそのまま災害時の対応をする組織と考えてください。そしてそのように組織を見直してください。
ここに一つ事例をご紹介します。
5月1日の日本テレビ、ザ・サンデーで放送されていたのもです。
JR西日本の脱線事故の際、消防・警察よりもいち早く現場に駆けつけ救助活動をしていた人たちがいました。事故現場近くの工場に働く200人の人たちです。
工場の一人が異変に気づき、すぐに上司に連絡しました。連絡を受けた社長は全員を食堂に集め、救助の支持をだしました。会社総出で救助にあたっていた様子も放送されていました。ガソリン臭に気づき、すぐに消火器を集めるよう指示をした人、そしてすぐに消火器を集められる人、咄嗟の判断で二次災害も防止しています。ご覧になった方も沢山いると思います。
この人たちは「阪神・淡路の大震災を体験された人たち」とコメントがありましたが、社長の指示を受け、日常から一変した非日常の活動を迅速に行っています。
防火管理組織と自衛消防隊組織のあり方を如実に表しています。
いざというときに動けなければ何の意味もありません。会社により組織は異なるでしょうが、こと危機管理についてはトッブダウンが大原則です。
危機管理を会社の差別化のためにも使ってください。それができるのは、社長!あなたしかいません。
次回は「防火対象物の定期点検報告」をとりあげます。
 消防計画を理解する事が最大のポイント(組織編)
消防計画を理解する事が最大のポイント(組織編)
防火管理者は消防計画を作成することが、大きな役割の一つです。
内容的には予防的な業務と万が一の災害に対応するための業務とに集約されます。
勘違いしないでください。防火管理者は防火管理業務を自ら汗水たらして行うのが本筋ではありません。
予防的な業務(以後、予防と称す)を行う防火管理組織と消火など有事の時に活動する組織(以後、自衛消防隊組織と称す)をどう組み立て、日常の手順にまでマニュアル化するかがポイントなんです。一人の防火管理者が何もかもできるわけがありません。ですから組織を使うんです。防火管理はセンスです!
会社の組織と防火管理組織・自衛消防隊組織をリンクさせる事ができれば、日常の手順に持っていくことが可能になります。
会社組織は別物で、消防に提出するためだけに消防計画を雛形どおりに作ってみてもなんに役にも立ちません。
消防計画は防火管理者が作成し、権原者(けんげんしゃと読み、一般的には社長)名で提出します。社長が公的に提出する書類です。いいかげんや間違いは許されません。ひとたび問題が発生すると会社の信用問題にもなりかねません。危機管理だと認識してください。
防火管理組織と自衛消防隊組織は裏表の関係です。
日常は防火管理組織が火災を予防し、火災時には自衛消防隊が活動します。同じ人間が2つの役割を持っていると理解してください。
組織ですから、ピラミッド型が一般的で分かりやすい!
ロケーションをまとめるピラミッド、複数のロケーションから部単位のピラミッド、部単位のピラミッドが集まった本部のピラミッドという様にピラミッドの頂点に責任者を置きます。どのような役職名かは会社により異なりますが、係長、課長、部長、本部長などが一般的です。
そして、ピラミッドの構成員毎に役割を明確にします。誰が、何を、どうするかが分からないと意味がありません。互いの事が理解できて、自分の役割が飲み込めるからです。そして、役割は誰が見ても分かるように、掲示することです。
周囲の抵抗もあるでしょうし、人事異動などで頻繁に変わるかも知れません。それでも、掲示し、いつでも最新の状態がわかるようにしておかなければなりません。そのようなシステムを作ることが防火管理者の仕事です。
うちの会社はどうだろう?どんな風に組み立てようと思案されたら、気軽に聞いてください。会社の規模、組織形態、複合ビル、単独ビルなどにより、一番スッキリする形を一緒に考えましょう。
くどいですが、ポイントは次の通り
① 防火管理はセンス!
② 防火管理者は消防計画を理解すること。
③ 会社組織にあった防火管理組織・自衛消防隊組織を作ること。
④ 防火管理組織と自衛消防隊組織は表裏一体の組織と理解すること。
⑤ 組織は個人名で掲示すること。
くどくて読みにくかったと思いますが、消防計画をあまく見ないでください。
ここが一番の勘所ですから。
次回は防火管理組織と自衛消防隊組織の表裏一体の説明とポイントを書きたいと思います。
<<前のページ
次のページ>>
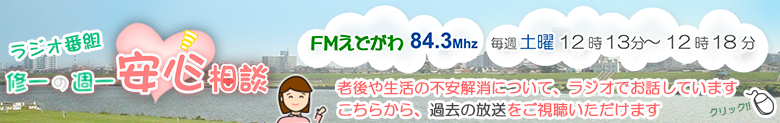
 |
 |
お問い合わせ/ご相談、ご不明な点などございましたら、是非お気軽にお問い合わせ下さいませ。
石井行政書士事務所 http://www.tokyo141.com/
| |
< 石井行政書士事務所トップページ
|
サイトマップ(このホームページの目次) |
|
| 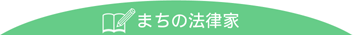





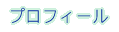

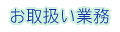

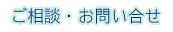




 共同防火管理のノウハウ
共同防火管理のノウハウ