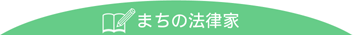 |
|
|

|
相続、遺言、成年後見、消防計画、防災計画、防火対象物定期点検報告制度
自衛消防隊訓練、防災教育、共同防火管理、会社設立、相続 等 おまかせください
|
TEL : (03) 3698-3914
FAX : (03) 3698-7539
東京都江戸川区瑞江1丁目19番11号
| |
|
|  |
|
|
 |
|
 頑張れ 防火管理者!(防火管理者って何?)
頑張れ 防火管理者!(防火管理者って何?)
「防火管理者の選任」って聞いた事があるでしょう?
防火管理者は社長から選任されて、防火管理業務を行う責任者です。
消防法第8条、第8条の2、第8条の2の2には防火管理者のすべき事が記載されています。建物の規模・用途・収容人数により甲種防火管理者か乙種防火管理者が決まります。個人住宅には防火管理者をおく規定はありませんが、集合住宅の場合は規模により必要となる施設もあります。
ここでは特に企業の防火管理者についてエールを送りたいと思います。
防火管理者に選任された皆様大変ご苦労様です。
甲種防火管理者は2日間の講習、乙種防火管理者は1日の講習を受け、終了後に効果測定が行われ結果、資格を取得します。
更に不特定多数の出入する建物で300人以上の収容人数の建物の甲種防火管理者は再講習を受ける事になります。
防火管理者の資格を持ち、防火管理者として選任されると、その責任はとても重いものとなります。なんと言っても、「社長から防火管理の事は君に任せる」と言われているのですから。
防火管理者の業務と責任が明確になった反面、やればやるほど周囲から浮いてしまうなんてこと、ありませんか?
防火管理者の方から資格は貰ったが、「なにをやればいいのか具体的によく分からない。」「やってはいるのだが、協力が得られない。」「総論賛成、各論反対、大事なのは分かるけど、そこまで必要なの?」などなど多くの悩みを耳にします。
果たして、防火管理者は何をどこまでやればいいのでしょうか?
答えは、簡単です。法律に基づいてきっちりやる事です!
おかれた状況がどうであれ、防火管理者として選任され、消防に届が出されている以上、防火管理者のあなたの責任を問われることになります。防火管理者として何をどうやるかはそれぞれの企業風土により異なるでしょうが、防火管理者のあなたの創意と工夫そして熱意が無ければできない仕事です。だからエールを送っているんです。
私は17年間、防火管理の専門の部署にいました。防火管理者をしていた事もあります。OLCでは現在非常に高いレベルで日常の防火管理が行われています。
文面で防火管理者にエールを送っても、なんの役にも立ちませんので、次回から具体的に防火管理者の業務について進めかたのヒントを書いていこうと思います。
2週間に一回のペースでお伝えできればと思います。
参考にしてください。
 神戸(三宮)に行ってきました。
神戸(三宮)に行ってきました。
2月1日の朝はとても気温が下がり、路面の凍結がありました。
早朝、坂になっている交差点があるのですが、50台の車両事故が発生したほどです。
タクシーの運転手さんに聞くと、「この辺は雪が少ないから、降ったら混乱するんだよ」とのこと。
もともと雪が多いように思っていたので意外でした。
(確か10年前の映像で雪が降っていたと思います。)
三宮は整然とした町並みですが、震災前の道路と変わったのかはよく分かりませんでした。復興というより復旧したという印象です。
震災のあの日、消防隊員の活動をまとめた手記が一冊の本になりました。
阪神大震災 消防隊員死闘の記 神戸消防局「雪」編集部 というものです。
今は絶版になっていますが、消防署の知人に参考にと頂きました。
そこには、火災現場で水がない・混乱・苛立ち・ナゼ・・とう困惑など、感じたままに書かれています。
救助できた事、できなかった事、PTSDに悩まされた事、沢山の消防隊員の思いが書かれています。
道路が渋滞で動けない。
無線が使えない。
ヘリから空中散布ができない。
今回の震災で築いてきた体制が何もできなかった・・今までの計画はなんだったのかと。
東京直下で地震が発生した時、同じ思いにならない事を本当に念願します。
人と防災未来センターに向かう道で、沢山の復興住宅(立派なマンションの町並み)が建っています。
被災者は避難場所から仮設住宅そして復興住宅へ移りました。
移れた人も震災前のような隣近所とは違います。
これも聞いた話なのですが、孤独死が深刻な問題のようです。
先日も復興住宅で一年半ぶりに老人が白骨化して発見されたそうです。
割合は分かりませんが、徐々に増えているようにも聞きます。
これって、本当に復興なのかな?と疑問符が・・。
自助、共助、公助ということが、阪神以後当たり前のように言われていますが、順序が違うでしょ?と正直思います。
国民を守るのは国の義務です。でも、国は手がまわらない。だから順序が逆になったんです。自分で守るしか方法がありません。現実的な方法です。
参考に・・
神戸の復興に際しては「神戸復興まちづくり機構」ができました。
東京でも、「災害復興まちづくり支援機構」が昨年暮れに立ち上がり、2月3日にはシンポジウムが行われました。
震災が発生する事を前提に、弁護士を初めとする士業(税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士、行政書士など)が連携を持って予防、復興にあたるというものです。
具体的な活動は、足立区、墨田区、新宿区、北区、葛飾区などで始まっています。
地域住民・コミュニティが中心になって活動し、機構が支援するという体制です。
①地域課題を知る。まち歩きなどで状況を把握する。
②避難所から復興を考える。
③仮設生活を考える。
④地域の復興計画を作る。
という順で行っているようです。
東京都ホームページ(http://www/metro.tokyo.jp)ni
東京都震災復興マニュアルがあります。
時間のあるときにご覧ください。
 地震は「リスク」ではない?・・!(ピキーン)
地震は「リスク」ではない?・・!(ピキーン)
先日、ある防災士の方とお話をする機会がありました。
その方は、次のように言っています。
地震を「リスク」ととらえている人が多いけれど、あれって、おかしいんだよ。
発生するか、しないか分からない事だから「リスク」なんだ。
でも、地震ははっきりと発生するとわかっている。
だから、対策しなくてはいけないんです!
ウ・ウ・ウー・ポロ
目から鱗です!(右目、左目から鱗が落ちました)
第2回目のコラムに 「地震対策:心がけ(明日はわが身と認識する!)」と書きましたが、私自身まだまだ心がけ甘い!と大反省です。
地震など倒壊家屋の下敷きになり身動き取れない時には、笛が効果的と言われています。その通りだと思います。
「リスク」の話を聞いた晩に、布団の中で生き埋めになったらと想像してみました。
するとすごい恐怖が襲ってきました。
暗い・時間が分からない・音が識別できない・狭い・喉が渇くし腹も減る・
火事がおきてるかもしれない・助けが来るのかこないのか・この先の見通しがつかない・・・どんどん悪い状況が浮かんできます。
果たしてこの状況に閉所恐怖症の私は耐えられるでしょうか?
布団の中での想像しているだけで、具合が悪くなりました。
人間ドックの脳ドックのとき体験したのですが、狭い真っ暗な音のあるのか、ないのか分からない空間にいると、時間の感覚がなくなっていくんです。
徐々に生きている実感が薄れていきます。不思議ですがそう感じました。
閉じ込められたらこうします!
「私は生きる・生きてやると強く念じる」
この執念が生き残りのエネルギーなのだと思います。
 企業生き残りのための防災対策 パート2
企業生き残りのための防災対策 パート2
12月22日の日本経済新聞に「日経の実施した地震対策調査」という記事がありました。
企業から見ると驚く結果、従業員からみるとそのとおりとうなづけるものだと思います。
勤務地で被災した場合、会社が混乱していても「自宅に帰る」、若しくは「帰るだろう」と7割の人が答え、更に自宅で被災したら、家族の無事が確認されても「出社しない」「おそらくしない」と5割が答えています。実に正直な数字だと思います。
この数字を企業はどうみるのでしょうか?
ここには、沢山のヒントが隠されています。
第一にやらなければならない事は、地震が発生した場合、会社としての方針を明らかにしておくことです。
従業員は帰すのか、残すとすれば誰を残すのか、出社させるのかさせないのか。誰を出社させるのか。より安全に移動するためにはどうするか?
企業はそれぞれの業種や分野で得意とするものがあるでしょう。
あなたの会社にあったものを探してみてください。100点の答えはありません。ポイントは「今より対策を進める事」が重要です。
歩いて帰る訓練をする。自宅までの地図を準備しておく。スニーカーなど歩きやすい靴を一足余分に置いておく。これらは自分でもできる対策です。
歩くにしても時間がかかります。
日没までに帰れますか?同じ方向の人と一緒なら、心強いし、安全性は高くなります。
これらは、会社側で整理してあげないと、混乱するだけです。事前の対策しか方法はありません。
企業生き残りためには、従業員のダメージをどれだけ少なくできるかが大きなポイントです。そのために、考え、工夫し、あなたの会社にあった対策を進める事が社長の責任だと思います。いくつかの企業ではすでに始めています。他社事例をそのままご紹介する事は控えます。この件でご質問がありましたら、お尋ねください。
 企業生き残りのための防災対策
企業生き残りのための防災対策
企業の防災対策で一番大切な事。
ズバリそれは従業員や家族の安全対策です。
残念な事に、重要な対策である反面、後送りにされている傾向が強いようです。
防火管理者の皆さん、経理者の皆さん、チョット考えてください。
地震が発生し、その結果、A社では従業員や従業員の家族の方に負傷者・死者が発生し、B社では死者や負傷者が発生しなかったとします。
A社では、事業の再開を検討することができるでしょうか?
お見舞いや葬儀の手伝いも発生するでしょうし、負傷した家族を残して従業員に出社するよう指示をする事ができるでしょうか?
会社は従業員の働きにより活動しています。その従業員が働く環境になければ、事業の早期再開はおぼつきません。
一方B社では、家族の安否を確認し出社してきた従業員により、復旧・事業再開ができる環境にあります。従業員のやる気!には大きな差が出ます。
地震の発生はどうにもなりませんが、従業員やその家族にまで安全対策・教育を施す事が、結果を大きく左右します。
「そんな事言ったって、会社はそこまで面倒見れないよ!」とおっしゃるかもしれません。でも、ここが分かれ目なんです。
「できない」の一言であきらめないで、一つでも、二つでも工夫してみてください。
きっと、あなたの会社にあったやり方が見つかりますから。
シンキングタイム
次回は、「こんな方法もありますよ」という例をご紹介します。
<<前のページ
次のページ>>
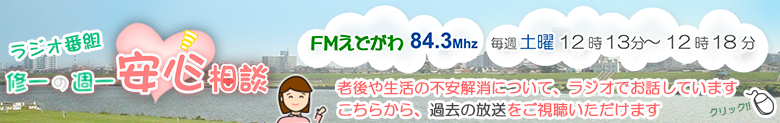
 |
 |
お問い合わせ/ご相談、ご不明な点などございましたら、是非お気軽にお問い合わせ下さいませ。
石井行政書士事務所 http://www.tokyo141.com/
| |
< 石井行政書士事務所トップページ
|
サイトマップ(このホームページの目次) |
|
|